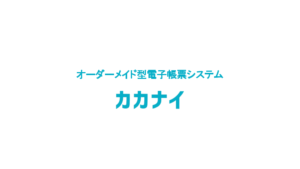第35回例会では「生成AI最前線」と題し、最新の生成AIツールの活用事例と料金比較について学びました

皆さま、こんにちは。広報担当の中山です。
8月の例会では「生成AI最前線」と題し、最新の生成AIツールの活用事例と料金比較について学びました。
1.今回の個人的な感想
生成AIは、画像・音楽・動画・音声・編集と幅広い分野で急速に進化しており、素人でも「そこそこ品質」のコンテンツを手軽に作れる一方で、プロはさらに高度な制作に活用できるようになっています。料金体系も無料から数万円に及ぶまで多様化しており、企業は目的や利用頻度に応じて柔軟に導入を検討できます。特にSNSや販促でのAI活用が当たり前になりつつある現状を踏まえると、中小企業にとっても競争力を高める大きなチャンスだと感じました。
2.今回の内容について
それでは今回の内容は以下のとおりです。
(1)教えてもらったこと
AIはすでにIQ120以上の頭脳に匹敵する能力を持ち、誰でも利用できるようになれば生産性が向上するのは明らかだと説明がありました。生成AIを導入済みの企業はまだ全体の9%程度と少なく、今のうちに活用を始めることで、人手不足が進む社会の中でも企業が生き残るための重要な武器となるとのことでした。実際の例として、中小企業診断士のCMを生成AIで制作し、その手軽さと実用性を実感する機会もありました。導入にあたっては、一気に全社展開するのではなく、まずは少人数で試験的に利用を始め、徐々に全体に広げていくことが成功の鍵であると強調されました。
(2)この技術によって企業が得られるメリット
生成AIの導入によって、無料あるいは低コストから利用を開始でき、業務にどう活用できるかをすぐに体験できる点が大きなメリットです。画像生成、音楽生成、動画生成、音声読み上げ、動画編集といった分野ごとに多様なサービスが用意されており、テンプレートや自動化機能を活用することで、専門知識を持たない社員でもすぐに使い始めることが可能です。たとえば、画像生成サービスの中には無制限で利用できるものもあり、SNSや販促用の素材づくりを格段にスピードアップできます。また、音声や動画の分野では、人間と見分けがつかないレベルの品質が近い将来実現しつつあり、企業活動の幅をさらに広げていくことが期待されます。
(3)導入にあたっての課題
ただし導入にあたっては、サービスや料金プランが多岐にわたるため、自社の利用頻度や目的に応じた選定が必要となります。さらに、複数画像の一貫性を保つことや、音楽生成で細部をコントロールすることなど、技術的な課題が依然として残っています。そのため、まずは試験的に利用して成果を出しやすい領域を見極め、段階的に社内での活用を広げていくことが重要であるとのことでした。
(4)中小企業診断士が支援できること
中小企業診断士としては、生成AIの最新サービスや料金比較を整理し、各企業に適した導入プランを提案できることが一つの支援ポイントとなります。さらに、実際の業務に即した活用シナリオを提示し、社員教育やテンプレート作成を支援することで、導入効果を最大化できます。また、生成AIの技術は進化が非常に速いため、常に最新の情報を収集し、企業に提供する役割を果たすことも求められています。
3.まとめ
生成AIは無料から始められるサービスも多く、導入のハードルが低いのが特徴です。その一方で、自社に合ったサービスを選び、段階的に社内展開を進めることが成果を大きく左右します。今後も当研究会では、生成AIの活用方法について研究を深め、中小企業の生産性向上や競争力強化につなげていくのが重要です。